普通に使っているとあまり気にならないが、ローキーな写真では中間部の明るさが違ってくる。
つまり写真の上と下で明るさが微妙に違っているのだ。
そこで、モニターをDell P2016 に入れ替えた。
アスペクト比16:10で、19.5インチのIPS ノングレア、解像度が1440x900である。
サイズと解像度は今までのI-O DATAのモニターと全く同じだ。
アスペクト比16:10のモニターはフィルム比の3:2に近く、写真では使いやすくて好きなのだが、
だんだんと少なくなってきているようだ。
 |
| i1Display Pro |
新しいモニターなので、とりあえずX-Riteの「i1Display Pro」を使ってDell P2016のキャリブレーションをしてみる。
「i1Display Pro」を使えばハードウェア キャリブレーションができないモニターでも、
ソフトウェア キャリブレーションをすることができる。
ハードウェア キャリブレーションは、白色調整、階調調整、輝度調整などを、
パソコンからの情報ではなくモニター自身で変換して色表示をする方法である。
それに対してソフトウェア キャリブレーションは、モニターの特性を測定した結果として作成されるICCプロファイルを基に、
パソコンのビデオドライバーなどで変換をしてモニターに表示される色を調整する方法である。
 |
| i1Profiler |
「i1Profiler」アプリを起動して、ユーザーモードは詳細にする。
次はワークフローセレクタから「ディスプレイープロファイル作成」を選ぶ。
キャリブレーションするディスプレイでDell P2016を選び、光源を「白色LED」にする。
白色点は「CIEイルミナントD65」で色温度6500Kを、輝度は120cdを選ぶ。
プロファイル設定はデフォルトを使う。
ガンマは2.2。
 |
| 「i1Display Pro」をモニターにセット |
ブライトネス、コントラスト、RGBゲインの調整にチェックを付ける。
モニターを工場出荷状態にリセット、「i1Display Pro」をモニターにセットして測定を開始する。
 |
| RGBゲインのテェック |
最初にコントラストのチェックが自動で行われる。
次にRGBゲインのテェックが行われ、左上に結果と調整パネルが表示される。
ここではRゲインの値に黄色の上矢印が出ているので、Rゲインを上げろということだ。
 |
| RGBゲインの調整 |
右下のモニターの設定メニューではRGBゲイン全てが初期値の100になっているので、
Rゲインを上げる代わりにGゲインを95、Bゲインを97に下げて白色調整をする。
これでRGBゲイン全てに緑色のチェックマークが付いて適正になった。
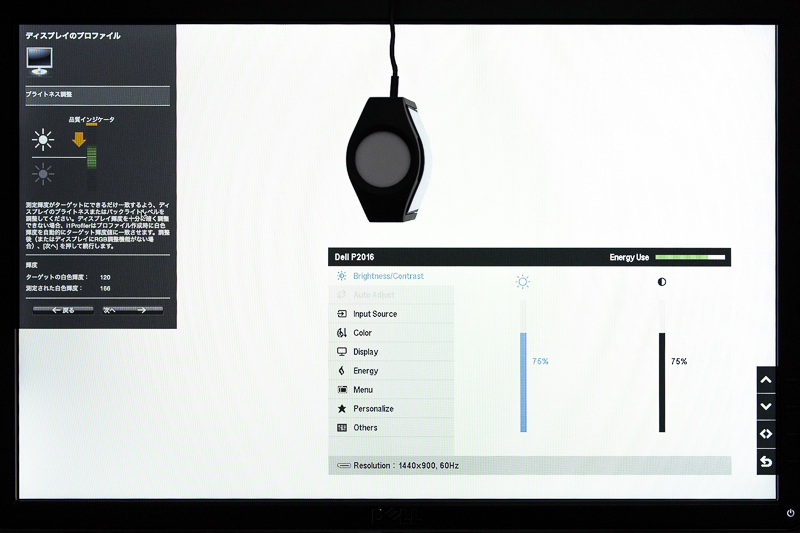 |
| 輝度のチェック |
次は輝度のチェックが行われ、結果と調整パネルが表示される。
ここでは、輝度を下げろという指示の黄色の下矢印が出た。
モニターの設定メニューでは輝度の初期値は75%になっていたが、43%に下げると目標値の120cdになり、
黄色の矢印が消えて緑色のチェックマークに変わり適正になった。
これで輝度の調整は終わりである。
 |
| キャリブレーション |
この後、モニター画面に様々なカラーを表示しながら、3分程度のキャリブレーションが続いた。
 |
| iccプロファイルの保存 |
キャリブレーションが終わると作成されたプロファイルが表示されるので、
保存すると自動的にモニターのiccプロファイルとして適用される。
キャリブレーション後のDell P2016は、以前のI-O DATAのモニターの時と、ほぼ同じ明るさと色再現になった。
これで上下の明るさの違いを気にせずに、クリアな画面で写真の調整ができる。

0 件のコメント :
コメントを投稿